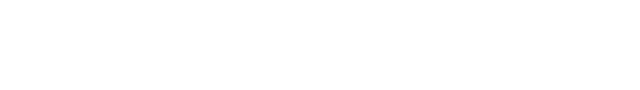8/16 院内勉強会「Jones骨折の評価とリハビリテーション」について
こんにちは、理学療法士の尾又です。今回は、「Jones骨折の評価とリハビリテーション」について勉強会を行いました。
Jones骨折とは、1902年にJones氏が報告した第5中足骨近位骨幹部の疲労骨折のことです。急な切り返し動作を繰り返すサッカー、バスケットボール、アメリカフットボール、ラグビーなどのスポーツで発症することが多いです。第5中足骨近位骨幹部に負担がかかる要因として、足部の外側での荷重があります。切り返し動作やステップ時、ジャンプの着地、キック動作において外側での荷重傾向が強いことが発症につながります。近年では、滑りにくい人工芝の導入やスパイクの影響により、サッカーやラグビーでの発症が増えてきています。
治療方針は、不完全骨折と完全骨折で分けられます。不完全骨折では、基本的に保存療法ですが、早期復帰を考える場合手術を選択することもあります。完全骨折では、手術(髄内スクリュー固定)が推奨されます。
評価では、立位姿勢や動作(片脚立位・サイドランジなど)を確認します。姿勢や動作の特徴や不良動作を把握し、その要因となっている筋力低下、筋の柔軟性低下、関節の可動域制限を確認します。注目するポイントとして、
①アーチの柔軟性低下→距骨下関節回外位につながり足部の外側荷重につながります。
②外側縦アーチの低下→足部外側への負担につながります。
③足趾把持筋力低下→Jones骨折を既往に持つ症例では足趾把持筋力低下(藤高ら2008,2012)があると報告されています。足趾把持力の低下は、足部のアーチ機能の低下につなが理、発症につながると考えます。
④股関節の内旋可動域制限→Jones骨折を既往に持つ症例では、股関節の内旋可動域制限(Saita et al2018)があると報告されています。股関節の内旋制限が、足部の外側荷重につながることが発症につながると考えます。
リハビリテーションでは、まず①アーチの柔軟性の改善、②外側縦アーチ機能の改善、③足趾把持力の強化、④股関節内旋可動域拡大を図ります。
①アーチの柔軟性の改善のために、足関節内果下方の載距突起から舟状骨の間に位置するバネ靭帯を理学療法士が触診しながら、外がえし動作を繰り返し、バネ靭帯の伸張性の改善を図ります。
②外側縦アーチ機能の改善のために、動的アーチ保持機構である腓骨筋の強化を行います。セラバンドを前足部につけて足部を外返しする事で腓骨筋の強化を行います。実施時の注意点として骨折部に負担をかけないようセラバンドの位置に配慮しながら強化を行います。
③足趾把持力の強化のために、タオルギャザー(足趾を曲げてタオルを引き寄せる体操)を実施し、足趾の屈筋の強化を行います。
④股関節内旋可動域の改善のため、股関節の内旋方向のストレッチを行います。
Jones骨折は再発が多いことが知られており、スポーツ中のプレーでの外側荷重の癖が残ることが原因と考えられています。このためリハビリテーションの後半では、外側荷重にならない動作の学習、獲得を図ります。例えば、片脚デッドリフトの姿勢で、セラバンドを母趾側で踏み、対側の手でセラバンドを引っ張るエクササイズ。母趾側でセラバンドを踏めていない場合は、セラバンドが抜けてしまいます。、母趾側での荷重のトレーニングとなります。さらに、スポーツ活動中の切り返しなどの動作で外側荷重にならないような動きを練習します。
これらのストレッチ、トレーニングなどは、自宅でも繰り返し取り組むことが、最初のない復帰には不可欠と考えています。
これからも皆さまの力になれるよう学び、学びに基づいて治療を実施します。よろしくお願いします。
理学療法士 尾又