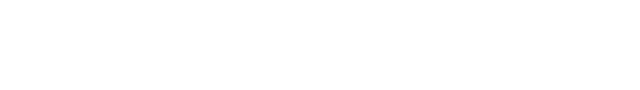8/18 院内勉強会「ランナーのハムストリングス肉離れとリハビリテーション」について
こんにちは。理学療法士の高橋(大基)です。今回は「ランナーのハムストリングス肉離れとリハビリテーション」について勉強会を行いました。
肉離れは、正式には筋挫傷といいます。スポーツ動作中に発症する筋損傷で、明らかな直達外力による筋打撲傷を除いたものの総称です。
ランナーのハムストリング肉離れには、①強力な大腿四頭筋の働きで振り出された脚が、接地動作に切り替わる際のブレーキ動作で生じるスプリント型、②接地時ハムストリングが収縮している状況で体幹が前屈し、股関節が屈曲し、ハムストリングの遠心性収縮が生じて受傷するストレッチ型の二つが存在します。
肉離れの特徴に、繰り返すことが多いことがあります。リハビリテーションでは、肉離れの原因となる筋の柔軟性の低下や筋力不足を改善するのはもちろん、応用能力を向上させることで再発リスクを軽減することができます。
柔軟性評価として、①前屈時に指が床まで届くのか、②うつ伏せで寝た状態で、膝を曲げた時に踵がお尻に届くのか、を確認します。
筋力評価として、①片足立ちが10秒できるのか、②うつ伏せで膝を曲げる力に左右差がないのか、③仰向けの状態で足を挙げて、腰が反らずに足が挙げられるのか、を確認します。これらを評価した上で、それらの改善を図ります。
さらに競技復帰に向けた応用能力トレーニングでは、「支える」、「のりこむ」、「跳ねる」の3つの要素にわけて実施します。
「支える」では、両脚で体を支える筋力をアップさせることが目的です。スクワットやお尻上げを行います。
「のりこむ」では、左右への動揺を抑制する筋の使い方を学習することが目的です。フロントランジやリバースランジを行います。
「跳ねる」では、機敏性(アジリティー)の向上が目的です。ジャンプやジャンプして足を組み替えるスプリットジャンプを行います。
この3つの要素に合わせたトレーニングを、自重からはじめて負荷量や動作スピードを上げることで、さまざまな場面での動作修正が可能になり、再発予防につながると考えています。
今回の勉強会では、”ランナーのハムストリングス肉離れ”に対するリハビリテーションの流れと具体的な治療法について学びました。
地域住民の方々やスポーツ愛好家が、長くスポーツに関われるよう機能改善から再発予防までサポートしますのでこれからもよろしくお願いいたします。
理学療法士 高橋大基